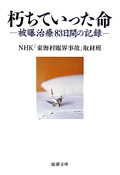浅暮三文『ポケットは犯罪のために 武蔵野クライムストーリー』(講談社ノベルス)

浅暮三文『ポケットは犯罪のために 武蔵野クライムストーリー』
を読んだ。
この人の作品はデビュー作『ダブ(エ)ストン街道』からのらりくらりと読んでいる。出る端から買い揃えるほど夢中なわけでもないのだけれど、書店で見掛けるとつい買ってしまう。そもそも同じ作家ばかりを読む性質ではないから、ある意味中毒性のある作風なのかもしれない。
デビュー作がいきなりの超異色ミステリだったこともあって、名前が頭にこびりついてしまったということもある。この人の筆にかかると、至極現実的な設定の小説さえ、否応なくファンタジックな印象を帯びてくる。深刻なはずの話題がそこはかとない滑稽に化ける。
この作品は雑誌で発表済みの6つの短篇に、7つのサイドストーリーを書き下ろしてひとつに繋いだものだ。なかなかに凝った造りの短編集である。この書き下ろし部分と、それに付随するラストの仕掛けこそが、この作品を1冊の本として読む場合の肝となる。
実際、それぞれの短篇だけを読めば連作にさえなっていない。
だからこそ、普通の短篇集として読んでも、それはそれで十分に面白い。意外にも真っ正直な日常の謎系ミステリである。日常といいながら、妙に浮世離れした可笑し味を感じるのは、やはり著者らしい軽妙なセリフ回しや個性的なキャラクターのお陰だろう。
ちょっとした奇妙な出来事に遭遇した市井の人たちが、謎に惹かれるようにして推理を始める。すると、些細なズレの向こう側に、意想外に深刻な人の業が横たわっていたりする。この辺りのバランス感覚が、軽妙ながら空疎にならない所以だろうか。
さらに、ここに描かれる出来事の多くは、実をいうと日常の謎の少し先を行っている。謎は日常の中にあるのだけれど、その真相は必ずしも日常の範疇にない。つまり、事件なのである。日常の中に紛れこんだ事件の断片から非日常的な真相にたどり着く。
いかにも正統のミステリである。
こうした個々のクオリティを踏まえた上での遊びが、今回のノベルス化で追加された仕掛けなのだろう。もしかすると好き嫌いの分かれる趣向かもしれない。それでも、著者のミステリに対する愛着や、旺盛なサービス精神は十分に感じ取ることができる。
浅暮クオリティを知るにはお誂え向きの短篇集だと思う。